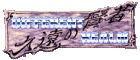
|
|
�@���[�ށA�ǂ������������Ă��u�k�쎁�v��u�g�D���[�E�������v�̘b���o�Ă��Ȃ��B
���ł��Ă��܂����̂ł��傤���B
�@���ꂾ���́u���E�v������Ă��Ȃ���A����Ԃ̋��Ԃɏ����Ă����� Verle a Zholl �̂悤�ɁA
���ꂽ���E�Ƃ����̂́A�͂��Ȃ����̂Ȃ̂ł��傤���ˁ[�B
�@�Q�[�����������グ�ɂȂ������́A�Q�[���̃}�j���A��������ꖇ�ŁA �������}�j���A���炵�����̂��u�f�B�t�@�����g�E�������v�̐��E�ς̐����������̂� �����ꂽ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B����́E�E�E �}�j���A���̃y�[�W�𑝂₷�\�Z���Ȃ������̂ł���܂��B(���Ԃ�)
�@���đO�u���͂Ƃ������A���̃Q�[���̐��E�ς̃x�[�X�ł���u�g�D���[�E�������v�̉���Ȃ��ɂ� �ƂĂ��Q�[���̉���Ȃǂł��܂���BWEB�Ȃǂʼn���̃����N�������Ȃ����߁A �Ƃ肠�����u�f�B�t�@�����g�E�������̐��E�ݒ�v�S�����ȉ��ɋL�ڂ��܂��B
���� �k��@��
�C���X�g ���� ���F
�@�g�f�B�t�@�����g�E�������h�̕���ƂȂ�̂͂ЂƂ̘f�����E�ŁA�ǂ����̌��m��ʉF���ɑ����Ă���A�n�������͂邩�ɑ�^�̘f�����B�����A���Ɍ��錎�i�q���j���S���邱�Ƃ������A�n���Ƃ悭���Ă��āA�d�͂��C�̑g���Ȃǂ̊�{�I�Ȑ����͂قƂ�Ǖς��Ȃ��B
�@���̘f���́A���a���n���̖�S�{������A�\�ʐςɎ����ẮA��50�{�ɂ��Ȃ�L��Ȑ��E���B�f���̕\�ʂ̓̈�߂����߂�̂��C�ŁA�C�m�ɂ͎O�̑嗤�Ƒ傫�������܂��܂Ȗ����̓���������ł���B
�@�����ɂ́A�َ��Ȃ������ō��x�Ȕ��B�𐋂����������A�������̎푰�ƍ��Ƃɂ킩��ĉh���Ă���A�Ȋw�Z�p�ɂ��Ă��A�����I�Ȗʂł͒x��Ă�����̂́A���_�I�Ȗʂł͒n�������啝�ɐi�����Ă���B
�@�����āA���̘f�����E�́A�����ŕ�炵�Ă���Z�l��������g�g�D���[�������h�i�܂��́A�g�������h�j�ƌĂ�Ă���B
�@�g�D���[�������Ƃ������t�́A�u�^�Ȃ鐢�E�v�Ƃ������ʂȈӖ��������Ă���i����ɂ���ׂāA�P�Ƀ������Ƃ��������Ƃ��ɂ́A����́u���E�v�Ƃ��u��Ȃ�f���v���炢�̈Ӗ������Ȃ��j�B
�@���̓��ʂȈӖ��ɂ́A���̐��E�̓N�w�҂����̎v�z�����f����Ă���B
�@�N�w�҂����́A�F���S�̂𑽗l���ɕx�������̐��E�����s���đ��݂��鑽���F���ƍl���A����Ɏ��������̐��E���F���̒��S�ɍ����鐢�E���Ɛ��������B�������̑��l�ȉF���̒��S�ł���Ƃ������Ƃ́A�t�ɂ����鐢�E�̉\�������ׂĔ�߂Ă���Ƃ������Ƃ����Ӗ�����B����́A�����������Z�ސ��E�������^�Ȃ���݂ł���A���̐��E�͂��̉e�ɂ����Ȃ����炾�I
�@�N�w�҂����������l�����̂ɂ́A������R������B���̐��E�ɂ́A����قǑ��l�Ȑ����̂��Ȃ��ω��Ƃ������̂����ӂ�Ă������炾�B
�@���Ƃ��A�g�D���[�������ɂ́A�n����ɂ͌����Ȃ����푽�l�Ȑ������������������Ă���B�������A�������������������̒��ɂ́A�ǂ�����Đi�����Ă����̂��z�������Ȃ��قLjَ��Ȑ��������݂���B���̂����A������ɑ����鐶�����ł��A���т����������̕ώ�Ⓙ��Ȃǂ����ݗ��Ƃ���ẮA�����ɂ�����ω�������ɕ��G�ōی��̂Ȃ����̂ɂ��Ă���B
 �@�܂��A�g�D���[�������̂��Ƃ�������邤���ŁA�Y��ĂȂ�Ȃ����̂Ɂg��j�����l�h�Ƃ��̈�Y�̂��Ƃ�����B
�@�܂��A�g�D���[�������̂��Ƃ�������邤���ŁA�Y��ĂȂ�Ȃ����̂Ɂg��j�����l�h�Ƃ��̈�Y�̂��Ƃ�����B
�@��j�����l�Ƃ́A���݂̕�����������O�ɁA�����N���̑��Âɉh������������z�����l�ނɎ����푰���B���̐�j�����l�ɂ��Ďc����Ă���肪����͏��Ȃ��A�ǂ��������푰�������̂��͂悭�킩���Ă͂��Ȃ��̂����A���@�ɕC�G����قǂ̋���ׂ����x�ȉȊw�Z�p�������Ă������ƂƁA��œI�ȏI���푈�ɂ���ĖŖS�������Ƃ����͒m���Ă���B�f���̒n�\�ɂ́A���̐�j�����l�̈�Ղ��������c����Ă���A��Ղ��甭�@������j�����̈�Y���A���݂̕����̔��B�𑣂����̂��B
�@�������A��j�����l�̋Z�p�͂͂��܂�ɂ������ŁA��Ղ��甭�@���ꂽ�@�B�ނɂ́A�I�v�̎����o�Ă����ɂ��ւ�炸�A���̂܂g�p�ɑς����Ԃɕۂ���Ă������̂�����A�C��������イ�Ԃ�g������̂������������B���̌��ʁA���݂̃������ł́A��j�����̉��b���Ĕ��B�����Y�Ɗv�����x���̋Z�p�ƁA��j�����̒��Z�p�����݂���Ƃ����A���Ɋ�ȃe�N�m���W�[�̌n���m������Ă���B���e�ƃr�[���K���A��s���ƃt���C���[�̋����Ȃ��A��Ƃ��Ă킩��₷�����낤�B
�@���̐�j�����l�Ƃ��̈�Y�̑��݂��A�������̑��l���Ɉ���Ă���킯���B
�@����͂Ƃ������A�g�D���[�������͍L��ŁA���̂Ԃ����R�̋��Ђɖ������������E���B�C�͉ʂĂ��Ȃ��L����A���ɖڂ������Ă݂Ă��A�����ɂ͐��܂œ͂����̂悤�ȎR���������藧���A������W�����O���͂������Ȃɕ����̐N�������ݑ����Ă���B�l�Ԃ��n�߂Ƃ���m�I�푰���Z��ł���̂́A�S�f���̂킸���\���̈���x�ɉ߂����A��͐l�Ֆ����̔鋫�Ƃ��Ďc����Ă��邾�����B
�@�������ł́A�ǂ�قǕ��������B���Ă��A���ꂾ���ł͎��R�̖҈Ђɑ����ł����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�����ŁA���������R���ɓK�����Đ������т邽�߂ɁA���\�͂ł���T�C�I�j�N�X�̔\�͂����B�����B����́A���ɕ������܂������B����������ɂ́A�d�v�ȈӖ��������Ă����B�������̒m�I�푰�́A�����ꂽ�T�C�I�j�N�X�̔\�͂Ɍ㉟������āA������z���Ă����ƌ����Ă��������炢���B
�@�������ŃT�C�I�j�N�X�́A�t�@���^�W�[���E�Ŗ��@�i�▂�p�t�j��������Ă���̂Ƃ͈���āA�������̈�ʐ����ɐZ�����Ă���B���Ƃ��A�傫�ȊX�ɂ̓e���p�V�[�\�͎҂����āA�ʐM��i�̂������Ƃ߂Ă��邵�A�a�@�ɂ͈�t�ƂƂ��Ɏ����\�͎҂��ҋ@���Ă���B�e���L�l�V�X�\�͎҂┭�Δ\�͎҂Ȃǂ́A�ӂ������R�l�Ƃ��Ĉꍑ�̌R���ɍ̗p�����B���̂悤�ɁA�T�C�I�j�N�X�́A�Љ�ɂƂ��ċM�d�ŗL�v�ȍ˔\�Ƃ��ĔF�߂��Ă���B�t�ɕ��������B�������݂ł́A�D�G�ȃT�C�I�j�N�X�\�͎҂������Ă䂭����ŁA�T�C�I�j�N�X�̑��݂͂܂��܂��d�v������Ă���̂��B
 �@���đ��́A�l�Ԃɂ悭������{�̑O�������A�����������Ɏ����푰�ŁA�S�g���H�тɕ����A�w���ɂ͑傫�ȗ��������Ă���B����g���l�h�ł���̂����̎푰�ȂB���ނƌ����Ȃ����Ă���炵���A�Q��Ƒ��𒆐S�Ƃ���Љ�\����A���x�ɂ���V��@�ȂǁA���Ƃ��Ă̐��i�𑽂��c���Ă���B�ڂ⎨�Ȃǂ̊��o�����ɉs���A�������ڂɂ��Ƃ܂�Ȃ��قǂ��₢���Ƃ��������B�L�����N�^�[�Ƃ��ẮA����ׂ邱�Ƃ��傫�Ȓ������B�����I�ɂ��ƂĂ��������ꂽ���̂������Ă��āA�l�ԑ��Ɏ����ō��x�ȋZ�p������z�������Ă���B
�@���đ��́A�l�Ԃɂ悭������{�̑O�������A�����������Ɏ����푰�ŁA�S�g���H�тɕ����A�w���ɂ͑傫�ȗ��������Ă���B����g���l�h�ł���̂����̎푰�ȂB���ނƌ����Ȃ����Ă���炵���A�Q��Ƒ��𒆐S�Ƃ���Љ�\����A���x�ɂ���V��@�ȂǁA���Ƃ��Ă̐��i�𑽂��c���Ă���B�ڂ⎨�Ȃǂ̊��o�����ɉs���A�������ڂɂ��Ƃ܂�Ȃ��قǂ��₢���Ƃ��������B�L�����N�^�[�Ƃ��ẮA����ׂ邱�Ƃ��傫�Ȓ������B�����I�ɂ��ƂĂ��������ꂽ���̂������Ă��āA�l�ԑ��Ɏ����ō��x�ȋZ�p������z�������Ă���B
�@�g�D���[�������ɂ́A���܂��܂ȕ������Ƃ����݂���B
�@�������A�f���Ƃ��Ẵg�D���[���������A���O��ɑ傫���L�����E�ł��邱�Ƃ́A�O��ł��G�ꂽ�ʂ�B�\�ʐς��n���̖�50�{�Ƃ����L���́A������z���������܂������Ă��A�ƂĂ��z���������Ƃ������̂���Ȃ��B���̍L��Ȑ��E�ɂ���ׂ�ƁA�悤�₭�Y�Ɗv���̃��x���ɒB��������̂����₩�ȋZ�p�������x�ł́A���قǂ̗͂������Ȃ��ƌ����Ă��A���Ȃ����ԈႢ�ł͂Ȃ����낤�B���̂������ŁA�������ɋ��Z����l�̒m�I�푰�́A�f���S�y�����S�Ɏx�z���ɂ������Ƃ͂��납�A�ǂ��ɉ������邩�m�邱�Ƃ���A�܂������ɂł��Ă��Ȃ���ԂɂƂǂ܂��Ă���B
�@���̂��Ƃ������āA���̃������́A�m�I�푰�����Z��������z���Ă���̈�i�������j�ƁA�܂������̖��J�̗̈�i�����j�ɑ傫���킩��Ă���B�������A���ۂɕ������ɑ����Ă���ƌĂԂ��Ƃ��ł���̂́A�S�f���̂킸���\���̈���x�ł����Ȃ��A��͂��ׂĐl�Ֆ����̔鋫�Ƃ��Ďc����Ă���̂ɂ����Ȃ��B
 �@���̂��߁A�������ɂ͐��̃T���f�B�A�i�A���̃A�f���[�T�A�N���h�V�A�Ƃ����O�̑嗤�����݂���ɂ��ւ�炸�A��������������ƍ������낵�Ă���̂́A���̂����N���h�V�A����������̑嗤�����ɂȂ��Ă���B
�@���̂��߁A�������ɂ͐��̃T���f�B�A�i�A���̃A�f���[�T�A�N���h�V�A�Ƃ����O�̑嗤�����݂���ɂ��ւ�炸�A��������������ƍ������낵�Ă���̂́A���̂����N���h�V�A����������̑嗤�����ɂȂ��Ă���B
�@���̂����A�T���f�B�A�i�嗤�ł����A�܂������������嗤�S��ɍL�����z���Ă͂�����̂́A�A�f���[�T�嗤�ł͐��݉����̈ꕔ�ɏW�����Ă������B�嗤�������瓌�݂ɂ����ẮA���[���W�����O���ɕ�����Ă���Ƃ������肳�܂��B�N���h�V�A�嗤�ɂ��Ȃ�ƁA����܂łɊm�F���ꂽ�����ł́A�����ƌĂׂ���͉̂��ЂƂ��݂��Ă��Ȃ��B�����́A�܂��ɖ��m�̊댯���҂���Í��嗤�Ȃ̂��B
�@���̂悤�ɁA�L��ȃg�D���[�������ł́A�������ƂƂ����ǂ��A���|�I�ȍL����������関�J�̔����̑O�ł͂܂��܂������ۂ��ȑ��݂��B�f���̍L���ɂ���ׂ�ƁA�m�I�푰�̐l���͂��܂�ɏ��Ȃ��A���⑺�𒆐S�ɓ_�̂悤�ɋ��Z���Ă��邾���B����ǂ��납�A���̒��ɂ����J�̍r�삪�����c����Ă���悤�ȏ�ԂŁA������ڂ���Ӌ�����͎��R�̋��Ђ������Ă���c�c���̐��E�ł́A�m�I�푰���L�喳�ӂ̃t�����e�B�A�ɏ��o���Ă��������́A�܂������Ă��Ȃ��B
 �@�Ƃ͂����A�������̕������Ƃɂ͔��Ƀ��j�[�N�œ����I�Ȃ��̂������Ȃ��Ă���B
�@�Ƃ͂����A�������̕������Ƃɂ͔��Ƀ��j�[�N�œ����I�Ȃ��̂������Ȃ��Ă���B
�@���ɂ���Đ����̃V�X�e���A�Y�ƁA�����A�@���ςȂǂ��Ⴄ�͓̂��R�Ƃ��Ă��A�g�D���[�������Ȃ�ł̗͂v�f�Ƃ��āA�푰��Ȋw�Z�p�̃��x���܂ł��قȂ��Ă���̂ŁA�����Ƃ̈�ۂ������Ԃ�ς���Ă���B
�@���Ɏ푰�̈Ⴂ�͑傫�ȈӖ��������Ă���B����́A�푰���Ƃɍ��Ƃ������̂ɑ���l�������̂��Ⴄ����ŁA���ɂ͍������Ȃ��푰������B���l���͕����𒆐S�Ƃ�����Q�̖����ŁA���̂悤�ȑ傫�ȏW�܂����邱�Ƃ��D�܂Ȃ����A���l��`�҂̗��呰�Ɏ����ẮA�����ǂ��납�\���l�K�͂̎��������̃R���j�[�i�Q���j�����̂����������ŁA���푰�̗̓y�̕Ћ��ŕ�炵�Ė������Ă���B�����������Ӗ��ł́A�܂Ƃ��ȕ������Ƃ�z�������Ă���̂͐l�ԑ��Ɣ��đ����炢�Ȃ̂����A���̓�̎푰�̊Ԃł����A�Ђƌ��ō��Ƃƌ����Ă��傫�Ȋu���肪����B�Ȃ�Ɣ��đ��ɂƂ��Ă̍��Ƃ́A��������̌Q�ꂪ�W�܂����A����ȑ��̏W���̂̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂��B
 �@�g�D���[�������̃e�N�m���W�[�́A�傫���킯��ƁA�g��{�Z�p�h�Ɓg���Z�p�h�̓�n���ɂ킯����B���̂����A��{�Z�p�i�x�[�V�b�N�E�e�b�N�j�́A�ڂ������̐��E�ŗ��j�ƂƂ��Ƀe�N�m���W�[���������Ɛi�����Ă����悤�ɁA���R�����I�ɔ��B�����Z�p�ƁA���̎Y���̂��Ƃ��Ӗ����Ă���B����ɑ��āA���Z�p�i�n�C�p�[�E�e�b�N�j�Ƃ����̂́A�����܂ł��Ȃ��A�_��I�Ȑ�j�����l�̋Z�p�Ƃ��̈�Y�̂��Ƃ��Ӗ����Ă���킯���B
�@�g�D���[�������̃e�N�m���W�[�́A�傫���킯��ƁA�g��{�Z�p�h�Ɓg���Z�p�h�̓�n���ɂ킯����B���̂����A��{�Z�p�i�x�[�V�b�N�E�e�b�N�j�́A�ڂ������̐��E�ŗ��j�ƂƂ��Ƀe�N�m���W�[���������Ɛi�����Ă����悤�ɁA���R�����I�ɔ��B�����Z�p�ƁA���̎Y���̂��Ƃ��Ӗ����Ă���B����ɑ��āA���Z�p�i�n�C�p�[�E�e�b�N�j�Ƃ����̂́A�����܂ł��Ȃ��A�_��I�Ȑ�j�����l�̋Z�p�Ƃ��̈�Y�̂��Ƃ��Ӗ����Ă���킯���B
�@�Q�[���̕���ƂȂ�g�D���[�������̌��݂́A�g�@�B�v���h�����S�N���߂���������ɓ�����B���̓�S�N���܂�̊ԂɃ������̐��E�͑傫���ϖe�𐋂����B��S�N�O�̃������́A�������݂��_�ƒ��S�̓S�핶������A�悤�₭���̒i�K�ł���H�ƒ��S�̋@�B�����ւƈڍs���悤�Ƃ��Ă����Ƃ��낾�����B
�@���̂���́A�܂���ʋ@�ւƌ����A�����Ȃ炵���R����A�����Ɉ������錡���ԁi�n�ԂɎ�����ցA�܂��͎l�ւ̖����͎ԁj�����Ȃ��A�Ɩ����ɂ��Ă��A�b�������������f�ȃ��E�\�N��A�X�X�̏o��I�C�������v���炢�����Ȃ������B�₪�Ė{�i�I�ȍH�Ɛ��Y���J�n����āA�ߕ��⓹��̗ނ����͖L�x�ɍs���n��悤�ɂȂ������A�e�N�m���W�[�͂܂��܂������B�ɋ߂������B����ł��A�H�ꂪ���݂���A���ƂƂ͂����A�������i���ʐ��Y����Ƃ������Ƃ́A�����ɂ����Ă͉���I�Ȃł����Ƃ������̂ł���B
�@�����A�g�@�B�v���h�̐������ƁA�͂�������l�ς�肵�Ă��܂����B�ߑ�Y�Ƃ̊�ՂƂ��ĕK�v�Ȃ���Ƃ������b�Z�p���A�قƂ�Lj��ɂ��āA��j�����Ƃ������̐�ˑR�킫�o���Ă����̂��B�����Ȃ����Ƃ��Ă��ӂ����͂Ȃ��B
�@�g�@�B�v���h�̓������{�i�����Ă����ߒ��ŁA�V���������A�J�����ꂽ��A���\������I�Ɍ��サ���Z�p�Ƃ��̎Y���͐������B������������Ă݂Ă��A�o�ዾ��]�����Ȃǂ̌��w�@��A�e��̍�����A���~�j�E���A�S���Ȃǂ̐V�f�ށA���v�A���d�@�A�{�d�r�A�X�v�����O�A�}�b�`�ȂǁA�ЂƂЂƂ��ח��ĂĂ������肪�Ȃ����炢���B
�@���̒��ł��A���ɐi���������������̂���ʋ@�ւ��B
�@�܂����̓��͋@�ւł��闬�̔����G���W�����J�����ꂽ�B���̃G���W���́A��j�����̋Z�p�����܂��Ƃ���Ȃ����p�����������̋Z�p�͂̐��Ƃ����ׂ����̂��B���̎d�g�݂́A�����̍��Z�x�̍����t��R���Ƃ���A���Ȃ��i�I�Ȑv�v�z�ō��ꂽ���R�@�ւȂ̂����A���o�͂ł���Ȃ���\�����ȒP�ŁA���Y���y���������Ƃ���A��������ɓƗ͂ŊJ���ɐ������Ă������C�@�ւ��A���p����҂����ɉߋ��̂��̂ɂ��Ă��܂����B
�@�����āA�����ɔ��ƂƂ��ɂ��̍ŐV�̃G���W���������V�^�̓��͑D���A����ɂ́A��{�Z�p�̎Y���ł͏��߂Ă̋���ԋ@�B�Ƃ��āA��s�D���o�������B�����Ƃ��A�������ɗL���̔��đ̂���邱�Ƃ͂܂��ނ��������A�q��@�̕��͉��Ƃ����p���ɑ��������邾���ł����A����ɕS�N���܂�̔N����K�v�Ƃ����B�������A���̊Ԃɂ��A��s�D�͐v�Ɖ��ǂ��J��Ԃ��Đ��\�����߁A���������イ�ő傢�Ɏ��Ă͂₳���܂łɂȂ����B���̕��y�Ԃ�́A��s�D��肪�D���Ɠ������炢�p�ɂɊX�Ŏp�����������邭�炢�Ȃ̂��B
�@�����A���̂Ƃ���A��s�D������Ȃɕ��y�����킯�́A���̗A���\�͂����邱�ƂȂ���A���Ԃ���������ł������ƁA�ǂ�Ȋ댯���҂��\���Ă��邩�킩��Ȃ����̗��ƈ���āA��̗��͂܂��������S����������Ȃ̂��B���݂ł́A��s�D�́A�������ꂽ�s�s�Ɠs�s�̊Ԃ����ԘA���D�Ƃ��āA�܂��A���Ղ�T���Ȃǂ̖ړI�ł����L���g�p����Ă���B
�@�������낢���ƂɁA�Ȃ��������Ԃ͂��܂��Ɏ��p���̃��h�������Ă��Ȃ����A����ɂ��ẮA�G���W�����܂���^�Ŏԑ̂ւ̓��ڂ��ނ����������ƂƁA�����Ŏ��炵�₷���n�����̋R�����A�������̎���Ƃ���ōD��Ŏg���Ă��邱�Ƃ��傫�Ȍ������낤�B
�@�������A�g�@�B�v���h�̉e�����ł�����������̂́A���ł��Ȃ��A�푈�̓���ł��镐�킾�����B��������V�����푰�̗��j���n�܂��Ĉȗ��A�d���|�S�̌��ƍb�h���嗬���߂Ă������ɁA���ɖ{�i�I�ȉΊ킪������悤�ɂȂ����̂��B
�@�������ł́A���j�̑�����������Ζ�̑��݂����m���Ă������A�������ŕ���Ƃ��Ďg���悤�ɂȂ����̂͂����ŋ߂̂��Ƃ��B�������A���͂ȉΖC��e��Ȃǂ͂܂����݂����A�U���̍ۂȂǂɓ������e�Ƃ��Ďg������x�ł����Ȃ������B�퓬�̎�͂͂����܂ŁA�����\���|���������ċR���ɂ܂�����R����A���╀���ӂ邤�����������B��ѓ���ƌ����|���|�̂��ƂŁA�����������イ�Ԃ�ȈЗ͂������B
�@��������ꂽ�̂��A���͂ȉΗ͂Ƒ��ː��\�����킹�����e�ƃ��C�t���e�������̂��B
�@���������e��́A���̐V���������i�Ɠ������A��j�����l�̈�Y�����Ƃɂ��ĊJ�����ꂽ�B��j�����l���c�������̂̒��ɂ́A���R�̂��ƂȂ���A�e�۔��ˌ^�̏e����n�߂Ƃ���e��̌g�щΊ���������B�������̋Z�t�����́A��������Ζ���g�p����e�̃A�C�f�A�ƁA��������̂ɕK�v�ȋZ�p���w�̂������B
�@�������A�����ł́A�Ζ�e�Ƃ����A�C�f�A����ɂ����āA�����̂������ʂ邽�߂ɁA��J���Ȃ���H�v���d�ˁA�v���ϋl�߂Ă������킯�ł͂Ȃ��A�i���Â̈�Y�Ƃ͂����j�ǂ̓_���猩�Ă����Ɋ����ς݂̌�������ɂ����āA�����������R�s�[������������̂��ƂȂ̂ł���B�������ŁA�������ɂ́A�Γ�e��}�X�P�b�g�e�Ƃ������e�픭�B�j�̑O�̒i�K����������āA�����\�̋ߑ�Ί킪�����Ȃ�o�����Ă��܂����̂��B
�@�����̏e��́A�e���ォ�瑕�U����㑕�e�Ƃ����^�C�v�ŁA�e��͈����₷���������Ɏ��߂��Ă���A�N�ł��ȒP�Ɏg�p���邱�Ƃ��ł�����̂��B���\��З͂́A�������ɏo�Ă���e�Ǝ����悤�Ȃ��̂ŁA�����ڂ̊������قƂ�Ǖς��Ȃ��B���{���o�[��o�[�A�N�V�����E���C�t���A��A���̃V���b�g�K���Ȃǂ��B�����I�ȃI�[�g�}�`�b�N���e������ɂ͂��邪�A������͐M�������Ⴍ�A�̏Ⴕ�₷���B�悭�A�N�V�����f��ȂǂŖڂɂ���悤�ȍŐV�^�̏e���́A���\�������邵�З͂��ア�킯�����A����ł��e�Ƃ��Ă͂��Ȃ�̂��̂��B�������A�@�֏e�Ȃǂ̎����Ί킪���������̂́A�i������g�D���[�������ł̂��ƂƂ͂����j�܂����炭�͐�̘b�ɂȂ邾�낤�B
�@����ɁA�e��Ƃ��ẮA�Ζ̏e�̂ق��ɂ��A�����K�X�ō|�S���̃_�[�g�������o���g�_�[�g�K���i�˖�e�j�h���J������Ă���B������́A��Ɍ�g�p�Ǝ�p��ړI�Ƃ����e�ŁA�e�ۂł���S��ɓł���h���Ďg�p�ł���̂��傫�ȓ������B�������A�K�X�����̂��߁A�Ζɂ���ׂĎ˒������Ȃ�Z���Ȃ�Ƃ������_�������Ă���B���̃_�[�g�K���́A�Ζ̏e����ł悤�₭���p�����ꂽ�ŐV�^�̕���Ȃ̂��B
�@����͂Ƃ������A���������e��̏o���́A�������ɂ�����푈�̗l���ƕ���̑̌n��傫���ω������Ă��܂��ɂ��イ�Ԃ����B���ĉΓ�e�̏o���Ő퍑�̐��̐��͐}���h�肩�����Ă��܂����悤�ɁA�e��͊e���̌R���̊Ԃɂ܂������ԂɍL�܂����B�@�B���������_���鍑�J�C�A�l�X�̐_�a�R�m�c�ł����A�e��̓����ɂ͔M�S�������قǂ��B
�@�������A�e��ɂ��둼�̔����i�ɂ���A�J���͂��ׂĐl�ԑ��̎�ɂ����̂������B���đ��̕����������Z�p���x�����ւ��Ă������A�l�ԑ��ɂ͂킸���ɋy���A��j�����l�̈�Y���������ė����ł���i�K�ɂ܂ł͒B���Ă��Ȃ������̂ł���B�{���Ȃ烌�����̎l��푰�̒��ōł������m�͂����͂��̗��呰�́A�@�B�ɂ͂���قNJS�����Ƃ��Ƃ��Ȃ��������A���l���Ɏ����ẮA��ՂɊւ�邱�Ƃ���悵�Ƃ͂��Ȃ������B
�@���̂��߁A�e��̏o�����A�������̕���̌n�����S�ɓh�肩���Ă��܂��悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ������̂ł���B�l�ԑ����������̎O�푰�́A�ˑR�Ƃ��ď]���̓�����|��ɗ����Ă������A���̐l�ԑ��ɂ��Ă��A�e�ƂƂ��ɕK�������̗ނ��g�т���̂��ӂ��������B�܂��A�e��͔��ɍ����ŁA���i�Ƃ��ďo��鐔�����Ȃ��A�N�����e�����Ă�킯�ł��Ȃ������B�S�̓I�Ɍ���ƁA���݂̃������ł́A�e�����҂̐����Q���Ƃ��āA�c��̂W�����e���������A�̂Ȃ���̕�����g�p���Ă���ƌ���̂��������B
�@����ɁA�ǂ��炩�ƌ����ƁA����ł��铁�����h��ł���Z�̕����A�e��o���̉e��������Ɏ茵����������ƌ����邾�낤�B
�@�e��̏o���ŁA������݂�������肩�A���Ă���҂��e�e�̕W�I�ɂ����˂Ȃ��d���ȋ������̃v���[�g�A�[�}�[�i���Z�j�͈ꕔ�̏d���R���̌R���������Ďp�������A�����ƌy���ē����₷���A�h��Ɩh�e�A���ʂŌ��ʂ������h��D�܂��悤�ɂȂ����̂��B���݂ł́A�v���̖h��ɃX�`�[�����̃��b�V���ߍ����̂�A���̖h��ɔ킹�Ďg���A��������h�삷�鑕�b�Ȃǂ��L���g�p����Ă���B���̂����A�ŋ߂ł́A�S�g���G�Ȃ��������S�Z�𒅂�悤�Ȗ��ʂȂ��Ƃ͂�߁A�K�v�ȂƂ���ɂ��������Z�𒅂���X�^�C�����嗬�ɂȂ��Ă��Ă���悤���B
�@���āA�����܂ł͎�Ɍ��݂̃������̃e�N�m���W�[�A�܂�A��{�Z�p�Ƃ��̔��W�Ɍ����Ęb��i�߂Ă������A��������͐�j�����l�̒��Z�p�̎��Ԃ����Ă݂邱�Ƃɂ��悤�B
�@�܂��ŏ��ɁA��j�����l�̉Ȋw�Z�p�̗͂��ǂ̒��x�̂��̂������̂���������Ă����ƁA����Ɋւ��ẮA�Ђƌ��Ō����ƁA�u�Ȋw�ɂ���ĒB���ł���Ǝv����ڕW���A���Ƃ��Ƃ����������Ă����قǁv�ƌ������Ƃ��ł���B�����Ƃ킩��₷�������ƁA�܂�́A�ނ�ɂ͕s�\�Ȃ��ƂȂǂȂ������Ƃ������Ƃ��B�u�i�Ȋw�͖��@�ƌ��킯�����Ȃ��v�Ƃ悭�����邪�A��j�����l�̒��Z�p�����́A�܂��ɖ��@�ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ������̂��B�����āA��j�����l�́A���̒���I�ȃe�N�m���W�[���v���܂܂ɍs�g���āA���̘f�������łȂ��A�F���S�̂����x�z���A���Ԃ��Ԃ���y���ɒ��z���Ă����킯���B
�@����������j�����l�̕����́A�����낵�����x�ɔ��B�����@�B����{�Ƃ��钴�@�B�����ŁA�ނ�̍��o�����@�B�ނ́A�܂�Ő������̂悤�ɕ��G�Ȏ��������Ǝ��ȏC���̋@�\�����킹�����A�قƂ�ǖ����ɋ߂����ԁA�����ɍ쓮���铮�͌�������Ă����B
�@���݃��������イ�ɓ_�݂��Ă����j�����l�̈�Ղ́A�قƂ�ǂ��P�Ȃ�c�[�ɂ����Ȃ����A�����Ƃ����^�𗯂߂Ă����Ղ���́A�����N���̗I�v�̎����o�Ă����ɂ��ւ�炸�A�ˑR�Ƃ��Đ\�����Ȃ��@�\����@�B�ނ���������������Ă���B
 �@��j�����l�̈�Y�̒��ɂ́A���Ƃ�l�̏��L�ƂȂ��āA���݂̃������ł����Ɏg�p���ꑱ���Ă���@�B�����Ȃ��Ȃ��B���Z�p�̎Y���́A�ǂ�Ȃɂ������Ȃ��̂ł����Ă��A���\���I������s���e�N�m���W�[�̐����W�߂����̂��B���̓_�A�ߔN�ɂȂ��Ă����璘�������B�𐋂����Ƃ����Ă��A���݂̃������̋Z�p�����ō��鐻�i�Ȃǂ́A����ɂ���ׂ�A�悭�����čH�̂�邢���v���J�̂悤�Ȃ��̂ɂ����Ȃ��B���Ƃ���A�N�����������Đ�j�����̋@�B��T�����Ƃ߁A��������L��������X��������̂����R�̂��Ƃƌ����邾�낤�B
�@��j�����l�̈�Y�̒��ɂ́A���Ƃ�l�̏��L�ƂȂ��āA���݂̃������ł����Ɏg�p���ꑱ���Ă���@�B�����Ȃ��Ȃ��B���Z�p�̎Y���́A�ǂ�Ȃɂ������Ȃ��̂ł����Ă��A���\���I������s���e�N�m���W�[�̐����W�߂����̂��B���̓_�A�ߔN�ɂȂ��Ă����璘�������B�𐋂����Ƃ����Ă��A���݂̃������̋Z�p�����ō��鐻�i�Ȃǂ́A����ɂ���ׂ�A�悭�����čH�̂�邢���v���J�̂悤�Ȃ��̂ɂ����Ȃ��B���Ƃ���A�N�����������Đ�j�����̋@�B��T�����Ƃ߁A��������L��������X��������̂����R�̂��Ƃƌ����邾�낤�B
�@�������A�l�Ֆ����̕Ӌ��̉��[���ɉB����Ă����Ղ����A�������牿�l����i�𐳂����I��Ŏ��������邱�Ƃ͒N�ɂł��ȒP�ɂł���Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B�������̒m�I�푰�̒��ł́A�l�ԑ�����j�����̈�Y�̊l���ɂ������×~���������A�^�悭��Ղ������o���Đ��҂ł����҂̐��́A�ߋ��̗�ł͐��S�l�ɂЂƂ肩�A����������Ȃ����炢�������B����ɂ́A����Ӗ��ł́A���z���@�肠�Ă邱�Ƃɓ������K�^���K�v�Ȃ̂��B
�@����������ł��A�ߋ��ɐ������̒T���Ƃ�R�t����Ղ̒T���ɒ���ł́A���܂��܂Ȕ����i�������������Ă����B�����āA�������������i�́A������͍̂��ɖv������A������͔̂���ɏo����A�܂�������͔̂����҂��l�I�ɂƂ��Ă����Ȃǂ��āA���傶��Ɉ�ʂ̐����̒��ɐZ�����Ă������̂ł���B
�@�������A�l�X���ŏ������j�����̋@�B�����Ŏ���Ă����킯�ł͌����ĂȂ��B
�@���������イ�Ԃ�ɔ��B���Ă��Ȃ����������Ə����̂���ɂ́A��j�����l�̈�Y�́A���̂悤�ɂ��炵�����@�̋@�B���A����ׂ������̎d�|�����Ǝv���Ă����̂��B
�@�����Ŏ����ɁA�g�p�@���쓮�������悭�킩��Ȃ����m�̋@�B���g�����Ƃ���ǂ��Ȃ邩�A�z�����Ă݂Ăق����B���܂�����A���̋@�\�̈ꕔ�����p���邭�炢�Ȃ�ł��邩������Ȃ��B�����A�\�z�̂��Ȃ��[���ȃg���u������������m�����A����Ɠ��������m���ɑ��݂���B����́A���X�N�̑傫���q���̂悤�Ȃ��̂��B
�@��j�����̋@�B���܂���Ȃ�ɂ��g�p�ł���悤�ɂȂ����̂��A�g�@�B�v���h�ɂ��ߔN�̃e�N�m���W�[�̑唭�W�����������炱���Ȃ̂ł���i���̂������ŁA���������̊�{�Z�p�̐��ʂ����������āA��j�����̋@�B���d���悤�ɂȂ����Ƃ����̂�����Șb�����j�B
�@�Ƃ���ŁA��������Ĕ������ꂽ��j�����l�̋@�B�̒��ŁA�������d�v�ȉ��l�������Ă�����̂ɁA�g�g�����X�|�b�h�h������B
�@����́A������������ȗ��^�̃J�v�Z���̂悤�ȋ@�B�ŁA���ɐl�Ԃ��ЂƂ�����V�[�g������A�V�[�g�̗�������˂��o����{�̃A�[���̐�ɂ́A�{�[�����O�̃{�[���قǂ�����傫�ȃN���X�^���̋ʂ��t���Ă���B�܂�A�l�Ԍ^�̐��������V�[�g�ɍ���ƁA�N���X�^���������̂��߂��݂ɖ�������悤�ɂȂ��Ă���킯���B���̋@�B�́A���̍������w�K�V�X�e���ŁA��������f�[�^�o���N�ɂ����킦�������A����̔]�̋L�������ɒ��ڃe���p�V�[�I�ɓ`�B���A������u���ɂ��Ċo�������邱�Ƃ��ł���̂��B��j�����l�́A�ǂ���炱�̋@�B���g���āA�K�v�Ƃ���m���ȕ����Ă����炵�������B
�@�����āA���̋@�B���ŏ��ɔ�����������T���Ƃ́A�E�C��U�邢�������ċ@�B�ɍ��������ƂŁA��j�����l�̌��t�Ɋւ���m�������������̂ł���B��j�����l�̌��t�Ƃ��̕����́A���݂̃������ł́g�镶��h�ƌĂ�Ă���A�����Ă��̃A�J�f�~�[�i�w�@�j�ŋ����Ă��炤���Ƃ��ł��邪�A������������ǂ�A���̒T���Ƃ��g�����X�|�b�h���犮�S�ȋ�������������Ȃ̂��B
�@�������A������Ղ�K�ꂽ���l���̐l�Ԃ����x�������Ă݂����ʁA�₪�ăg�����X�|�b�h�̎g�p�@����������𖾂����Ɏ���A���̏��́A��j�����l�Ƃ��̕����𗝉����邤���ŁA�����Ȃ��M�d�Ȏ����Ƃ��Ė𗧂Ă���悤�ɂȂ����B���̃g�����X�|�b�h�ɒ~�ς���Ă������̒��ɂ́A���e�����x�����ė�������̂ɉ��\�N���̌������K�v�ȍŐ�[�̉Ȋw���_�Ȃǂ�����A���̌����Ɉꐶ�������w�҂����Ȃ��Ȃ��B�������A�c�O�Ȃ��Ƃɂ́A�����킦���Ă������̑唼�́A���̎�����̌l�I�Ȏ�i�������A�ǂ�Ȏ�Ȃ̂��z�����邱�Ƃ����ł��Ȃ��悤�Ȏ�j�Ɋւ��閳�Ӗ��Ȃ��̂������̂��B
�@���̍ŏ��̃g�����X�|�b�h�́A���݂ł��C�V���������{�����L���A�ۊǂ��Ă��邪�A�@�B���ړ������邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ŋ@�B�̂�������Ղ̏�ɊX��z�����Ƃ�����b�́A���������イ�Ŕ��ɂ悭�m���Ă���B���̊X�����݂̎�s�C�V�������A�ł���B
�@�g�����X�|�b�h�ɂ��ẮA���̍��Ƃ�l�̎�ŐV���ɉ��䂩����������A���d�ɕۊǂ���Ă���ƌ����Ă���B�܂��A�������̃G���[�g�Z�t�𑩂˂钴���Ƒg�D�́g�Z�p����h�i�e�B�N���b�g�j���A�ő勉�̋L���e�ʂ������S�ȋ@�B�����鑠���Ă���Ƃ��\����Ă��邪�A���̐^���͒肩�ł͂Ȃ��B
�@��i�I�ȍ�����ʋ@�ւ́A��j�����l�̒z�������@�B�������x�����{�̒��ł��������B�@����́A�ڂ������̕�炷�����̐��E�ł����������A���B���������́A����ɂӂ��킵�����B������ʋ@�ւ�K�v�Ƃ�����̂Ȃ̂ł���B
�@��j�����l�́A�L��ȃ������̘f���S�y���x�z���Ă��������ł͂Ȃ��A���̎x�z�̗̈���F���̋��X�ɂ܂Ŋg�債�Ă����B���R�A���ꂾ���̋�Ԃ��x�z���ɂ����ɂ́A�c��ȋ��������̂Ƃ������ɍs�����ł��鍂���\�̌�ʋ@�ւ��K�v�ɂȂ��Ă���킯���B
�@����������j�����̌�ʋ@�ւ́A������������������Ďg�p����Ă���B
�@�܂������Ԃɑ���������̂Ƃ��āA�g�r�[�N���h������B
�@�������A���̎����Ԃɂ͎ԗւ��Ȃ��A�ړ����邱�Ƃ��ł���̂����ゾ���Ƃ͌���Ȃ��B����𑖂�Ƃ��ɂ́A�ӂ��n�\���ꂷ��ɕ����т������Ċ���悤�Ɉړ����邪�A�K�v�Ȃ�C��𑖂邱�Ƃ��A���������Ŕ�s���邱�Ƃ��ł���B
�@����́A����Ζ��\�̌l�p�g�����X�|�[�^�[�ŁA���l�̏�q���悹�āA���C������݂Ɉړ����邱�Ƃ��ł���̂��B
�@�܂��A���̃r�[�N���̒��ɂ́A��s�@�\�������Ȃ���o�̗͂����p�Ԃ�����A������́g�����h�r�[�N���h�ƌĂ�Ă���B
�@�����̎��q�́A��j�����l�ɂƂ��čł���ʓI�ȏ�蕨�������炵���A��r�I��������������Ă��邪�A�@�̂��ۗL����G�l���M�[�c�ʂɂ͌��肪����̂ŁA���ۂɑ����Ă���Ƃ������������̂͋H�ł���B
�@����ɍq��@�ɑ���������̂Ƃ��āA�g�t���C���[�h�Ɓg�I�[�j�[�\�v�^�[�h������B
�@�t���C���[�́A�L���̔��đ̂ŁA�W�F�b�g�G���W����P�b�g�G���W���Ȃǂ̕��ˎ��̐��i�@�ɂ���ċ���Ԃ킯�ł͂Ȃ����Ƃ������A�قƂ�nj���̔�s�@�ƕς��Ȃ��O�������Ă���B���i�͂Ƃ��ẮA�r�[�N���Ɠ������m�̃G���W�����g���Ă��邪�A�͂邩�ɋ���Ԃ̂ɓK���Ă���A�ō����x�Ɖ^�����\�����Ⴂ�ɍ����Ȃ��Ă���B
�@�I�[�j�[�\�v�^�[�́A�������đ̂ɂ��Ă��A�܂������Ⴄ���z�ō��ꂽ�@�B���B������́A�����ɍ��������O�������Ă���A�����Ŕ��U�����闃���g���ċ���Ԃ̂ł���B�@�ō����x���r�[�N�����͑������A�t���C���[�ɂ͉�������Ȃ��B�������A���̔��ʁA�^�����\�����͋��ٓI�ŁA�{���̍����ɕC�G����قǂ̋@���͂�����Ă���B
�@�i��j�����l�ɂƂ��āA�t���C���[���������W�F�b�g�@�̂悤�ȑ��݂��������̂Ɖ��肷��ƁA�I�[�j�[�\�v�^�[�͂����炭�w���R�v�^�[�̂悤�ȑ��݂������̂��낤�B�j
�@�������ɂ��������q��@�͔������ꂽ�������Ȃ��A�ɂ߂Ă߂��炵�����݂ŁA�قƂ�ǂ����Ƃ̏��L�ƂȂ��Ă���A�d�v�l���̗A����A���Ɩ��A��@�����ȂǂɎg�p����Ă���B
�@�������A���ƌ����Ă��A��j�����l���₵����ʋ@�ւ̒��ōł��d�v�ȋ@�B�́A��C�����z���ĉF����Ԃ�����s�\�Ȓ������F�����g�\�[���[�o�[�W�h���낤�B
�@���̃\�[���[�o�[�W�́A�������S�̂�T���܂���Ă݂Ă��A�킸�����@�����c�����Ă��Ȃ��Ƃ����M�d�i�ŁA���̂��ׂĂ����Ƃ̏��L�ɂȂ��Ă���B���̐��\�͂܂��ɋ����ׂ����̂ŁA�G���W���ɂق�̐��p�[�Z���g�̃p���[������Ă�邾���ŁA�܂������ԂɃ��������y���ЂƉ�肷�邱�Ƃ��ł��邭�炢�Ȃ̂��B
�@�\�[���[�o�[�W�́A���̂��܂�̍����\�Ɗ��l�䂦�ɁA��������Ă����x�����E�܂Ő��\�������ꂽ���Ƃ͂Ȃ��A���ۂɉF����s���s�Ȃ������Ƃ��Ȃ��B�ǂ̋@�̂��A���L���鍑�Ƃ̕ۊnjɂɈ��S�ɂ��܂����܂�Ă���A��قǍ����������K�v�ł��Ȃ���Ύg�p����邱�Ƃ͂Ȃ��B
�@���ꂱ���́A����Y�̒��̈�Y���ƌĂԂɂӂ��킵���@�B�Ȃ̂ł���B
�@��j�����l�̒��@�B�������x���Ă���������{�̒��ɁA�e�킳�܂��܂ȁg�X���C�u�}�V���h�ƌĂ�鎩���@�B������B
�@�����Ō��������@�B�Ƃ́A���炩���߃C���v�b�g���ꂽ���̎w���ɏ]���ĊȒP�Ȗ��߂����s���邾���̏����I�ȃ��{�b�g�Ƃ͈قȂ�A���ڎw�����Ȃ��Ă��ɉ����Ď���I�Ȕ��f���s�Ȃ����Ƃ��ł���A���x�ɐi�������@�B�����̂̂��Ƃ��B
�@��j�����l�́A�l�Ԃɂ�����ĒP���ȍ�Ƃ��s����ꂵ�炸�̘J���҂Ƃ��āA�͂��܂��A�l�̏]�l���q�Ƃ��āA���������X���C�u�}�V�����D��Ŏg�p���Ă����炵���B
�@���̂��߁A�������S�y�ɎU��鑽���̈�Ղ���́A�O���͌����ɂ�����A��ނ��@�\���܂������قȂ�X���C�u�}�V�������̂���������Ă���B
�@�@�B�̂̑����́A��j�������ŖS�����Ƃ��ɋ@�\�ɉ��炩�̏�Q�𗈂�������A�d����ׂ���l�������Ē����ҋ@��Ԃɂ�����̂��قƂ�ǂ����A���ɂ́A���݂Ɏ���܂ő��Â̖��߂𒅎��ɉʂ��������Ă�����̂�����B
�@�Ƃ���ŁA���������X���C�u�}�V���ɂ́A�ǂ�ɂ������\�̐l�H�]���g�݂��܂�Ă���A���t�����ʂ���A�����Ɏd����悤�ɋ@�B�̂�������邱�Ƃ��ł���̂��B�܂��A���Ƃ����t�ŋ��������邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ă��A�e�@�B�̂ƃy�A�ɂȂ��Ă���g�R���g���[���E�L�C�h����ɓ����A�������ő�����x�z���邱�Ƃ��ł���B�^�悭�X���C�u�}�V�����ł����Ƃ��ɂ́A�N�ɂ����̋@�B�̂̎�l�ɂȂ��`�����X������̂ł���I
�@���������X���C�u�}�V���́A�M�d�Ȍ����ޗ��ł���ƂƂ��ɁA���ꎩ�̂���j�����̐������ؐl�ł�����B�Z�p�����e���̃A�J�f�~�[�ł́A���̂��̋@�B�̂��Ǘ����ɒu���āA��j�����̈�Y�̌����ɖ𗧂ĂĂ��邪�A�����ޗ��ɂ���̂ł͂Ȃ��A���ۂɎg�p����Ă�������r�I�悭����������B
�@���Ƃ��A�G���W�j�A�Ƃ��Ă̋@�\�����@�B�̂��A������j�����̋@�B���C�����邽�߂Ɏg�p����Ă�����A��ËZ�p�҂Ƃ��Ă̋@�\�����@�B�̂��A�l�Ԃ̎�ł͕s�\�Ȏ�p��������肷�邽�߂Ɏg�p����Ă�����ƁA�������ꂽ�@�B�̂́A���̋@�\�ɉ����āA���܂��܂ȑ��ʂŃ������̐����ɍv�����Ă���̂ł���B
�@�������A�X���C�u�}�V���̒��ɂ͐퓬��ړI�Ƃ��č��ꂽ�댯�ȃ^�C�v�����݂���B����́A�����ʂ�̈Ӗ��ŁA�키���߂����ɍ��ꂽ�퓬�}�V�[���Ȃ̂��B
�@�퓬�p�̎����@�B�́A�g�}�V���r�[�X�g�h�ƌĂ�Ă���B�@�B�̂������₻�̑��̐������̎p��^���č���Ă��邩�炾���A���̓���Ɣ������x�ɂ��Ă��A�@�B�Ƃ͎v���Ȃ��قǂŁA�܂�Ŗ{���̐������̂悤�ɂ��₭���炩�ȓ���������B���̓_�ł��A�@�B�̏b�ƌ����ɂӂ��킵���Ƃ����킯���B
�@�������A���̋@�B�����́A�v���I�Ȑ�j�����̎E�l����𐔑����������Ă���B�b�͏b�ł��A�ӂ��̖ҏb�ȂǂƂ͂���ׂ��̂ɂȂ�Ȃ����炢�댯�ȑ��݂Ȃ̂��B
�@�}�V���r�[�X�g�́A���������d�v�Ȏ{�݂̌x���v���Ƃ��Ďg���Ă������̂ŁA�����̖ŖS�����т��@�B�̂́A�������p���ƂȂ������܂ł��A���Â̎g���𒉎��ɉʂ��������Ă���B�N���҂����Ղ���낤�Ƃ��Ďc�[�̒���p�j����}�V���r�[�X�g�ɎE���ꂽ�T���Ƃ̐��́A���Ȃ�̐l���ɂ̂ڂ邾�낤�B
�@�܂��A�����}�V���r�[�X�g�ł��A����ɋ���Ȑ퓬�\�͂����l�Ԍ^�̋@�B�̂́A�g�K�[�f�B�A���h�Ƃ��Ēm���Ă���B
�@���̃K�[�f�B�A���́A��̂Ń}�V���r�[�X�g���\�̂����킹�������̐퓬�͂�L���Ă���A��j�����₩�Ȃ肵����ɂ́A��e�͂Ȃ��G��r�ł��鎩���U������Ƃ��Ďg�p����Ă����炵���B
�@�K�[�f�B�A���̎����́A�܂����݂��m�F���ꂽ�킯�ł͂Ȃ����A���̑��݂��Î�����f�ГI�ȏ؋��͂�������������Ă���B���̏؋��ɂ��ƁA�K�[�f�B�A���ɂ͈�̂Ƃ��ē������̂͂Ȃ��Ƃ��A��l�ł��鏊�L�҂Ɛ��_�I�ɓ������邱�Ƃ��ł���Ƃ������Ă��邪�A���ꂪ�^�����ǂ����͒肩�ł͂Ȃ��B
�@������ɂ���A��j�����̈�Y���A�p�������̉��l��������̂���Ƃ͌���Ȃ��̂ł���B
�@��j�����l�̈�Y�����Ȃ�A�Ō�ɔ���ɂ��Ă��G��Ă����K�v�����邾�낤�B
�@�Ƃ���ŁA����Ƃ͈�̂ǂ�Ȃ��̂Ȃ̂��낤���H
�@����́A�����ɂ悭�������ʑ̂̌����\�����ŁA�̒��ɒW�������h���Ă���Ƃ��납��A����i���𒆂ɔ�߂��j�ƌĂ�Ă���B�������A����ɂ���ނ�����A����������̐F�͂��܂��܂ŁA�������ЂƂЂƂ����ɈقȂ��Ă���B
�@����́A�������ɕς�����ł���B�������A�ꌩ���������ł́A�߂��炵����������Ɍ����邭�炢�ŁA���̖̐{���̉��l��z�����邱�ƂȂǂł��Ȃ����낤�B
�@�����������͎̐��R�ɂł������̂ł͂Ȃ��B���R�ɎY������̂ł͂Ȃ��A��j�����l�ɂ���Đl�H�I�ɍ��ꂽ���̂Ȃ̂ł���B
�@���̂Ƃ���A����́A�c��ȃG�l���M�[��ۑ����Ă������߂̗e�ꕨ�Ȃ̂ł���B����Έ��̔R���d�r���B�������A���̏ꍇ�A���ɕ������܂�Ă���G�l���M�[�̑��ʂ́A�D�Ɍ�������ɂ��C�G����B��j�����l�́A��ʂ̃G�l���M�[���ȒP�A�����S�ɂƂ舵���ЂƂ̎�i�Ƃ��āA����ݏo�����̂��B��j�����l�̋@�B�́A���ׂĂ��̔���͌��Ƃ��Ă���̂ł���B
�@�����Ƃ��A����ȊO�Ŕ���ɂ��Ă킩���Ă��邱�ƂƂ����A�̏o�����̐F�ɂ���ăG�l���M�[�̎�ނ��Ⴄ���ƁA���̋������G�l���M�[�̎c�ʂ�\�킵�Ă��邱�ƁA���������Ɋ�������A������肵�ċ@�B�ɂ����悤�ɉ��H���邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ��炢�ŁA�قƂ�ǂ���̂܂܂Ɏc����Ă���B
�@�������A����͋H�ɂ���������Ȃ����ƂƁA���̓��͌��Ƃ��Ă̕K�v������A����ȋ��K���l�������Ă���B����Ӗ��ł́A��j�����l�̈�Y�̒��ł��A�N�����������ɓ��ꂽ���Ɗ���Ă���̂́A���̔���Ȃ̂�������Ȃ��B
 �� �T�C�I�j�N�X�Ƃ͉����H
�� �T�C�I�j�N�X�Ƃ͉����H�@���\�͂ƌ����Ă��A���̈Ӗ�����Ƃ���͂܂��܂����B���Ƃ��A���\�͂��g�d�r�o�h�ƌĂԂ��Ƃ����邪�A���̂d�r�o�Ƃ́A�u�����o�I�m�o�v�Ƃ����Ӗ��ŁA�{���͒��\�͂̒��ł��A�l�Ԃ̐��_�ɔ�߂�ꂽ��U�̊��o�Ƃ��ẴN���A�{�����X�i�����j��e���p�V�[�i���_�����j�̂��Ƃ������w���Ă���B�����ɂ́A�N�����m���Ă���e���|�[�g�i�ϔO�ړ��j��e���L�l�V�X�i�ϔO���́j�Ȃǂ̒��\�͂͊܂܂�Ă��Ȃ��̂ł���B
�@�g�D���[�������ł̒��\�́A���Ȃ킿�A�T�C�I�j�N�X�́A�u�����̂̐��_�ɏh����ݓI�ȓ���\�͂ł���v�ƒ�`���邱�Ƃ��ł���B�ǂ�Ȑ������ł��A������x���B��������̈ӎ���L���Ă������A����͂Ƃ������A���̃T�C�I�j�N�X�̔\�͂������Ă���̂ł���B�g�D���[�������ɂ́A�����̐A���̂悤�ɁA�Q��S�̂łЂƂ̋^�����_�����o���A�T�C�I�j�N�X�\�͂����鐶���܂ł���B�������A�������Ō����Ƃ���̃T�C�I�j�N�X�ɂ́A�قڂ���Ƃ������ނ̒��\�͂��܂܂�Ă���B�d�r�o�ɑ�����\�͂�����A�g�T�C�L�b�N�h�i�e���|�[�g��e���L�l�V�X�Ȃǁj�ɑ�����\�͂�����B�����ڂ��ǂ�ȂɊ�Ȓ��\�͂ł��낤�ƁA�����Ȑ��_�ɂ��͂ł���A����̓T�C�I�j�N�X�̔��e�Ɋ܂܂��̂ł���B
�@���ɁA�l�ԑ����n�߂Ƃ��郌�����̒m�I�푰�́A���������R�ɑł������ĕ�����z���ɂ������āA�T�C�I�j�N�X�̔\�͂ɑ傫���ˑ����Ă����B���Ƃ��A��w�̒m���������B�������ߋ��̎���ɂ́A�����\�͂̎����傱�����A�����ЂƂ̎��Î�i�������̂��B�T�C�I�j�N�X�Ȃ��肹�A�����̃����������̑唭�W�͌����Đ������Ȃ������ƌ����邾�낤�B
�@��ʃT�C�I�j�N�X�\�͂́A���̐����̈Ⴂ����A���S�ɓƗ������V�n���̔\�͂ɂ킩��Ă���B�e�\�͂́A���ꂼ��g�v���R�O�j�V�����i�쎋�j�h�g�e���p�V�[�i���_�����j�h�g�e���|�[�g�i�ϔO�ړ��j�h�g�e���L�l�V�X�i�ϔO���́j�h�g�G���p�V�[�i������j�h�g�{�f�B�G���n���X�i���̋����j�h�g�q�[�����O�i�����j�h�ł���B
�@�v���R�O�j�V�����́A�����o�I�ɂ��̂�m�o����\�͂ŁA�ǂ̌�����������������A�����̂�댯�̑��݂������Ƃ邱�Ƃ��ł���B�ߋ��̌��i���̂�������A������\�m���邱�Ƃ��ł��A����ɂ́A��ŐG�ꂽ���̂�ʂ��āA���̕i���̗R����m������A����Ɋւ��̂��郔�B�W���������邱�Ƃ��ł���B
�@�e���p�V�[�́A�������̐��_�ɒ��ڎv�O�ɂ���ĐڐG���A�S�ƐS�ʼn�b������A����̎v�O��ǂ݂Ƃ�\�͂��B�Ö��Î��������đ��l���v���ʂ�ɑ�������A�܊������������Č��o�������邱�Ƃ��ł���B�t�ɁA���_�U������g����邽�߂ɂ��K�v�Ȕ\�͂��B
�@�e���|�[�g�́A��Ԃ̊u�������u�ɂ��Ĕ�щz���Ĉړ�����\�͂��B�������A���ꂽ�Ƃ���ɂ�����̂��Ƃ�邱�Ƃ��ł���A��Ԃ�c�߂Ď����̂͂��܂ɐ��肱�ނ��Ƃ��ł���B
�@�e���L�l�V�X�ɂ��ẮA��������܂ł��Ȃ����A�ȒP�Ɍ����A���G�ꂸ�ɕ��̂����\�͂��B�������A�����������������ł͂Ȃ��A��������p���Ă��܂��܂Ȍ��ۂ������N�������Ƃ��ł���B���Ɍ���M�Ȃǂ̃G�l���M�[�𑀂邱�Ƃ��ł���̂ŁA�e��r�[����h���h��V�[���h������A���e�������Ƃ��ł���̂��B
�@�e���L�l�V�X�́A�p�C���L�l�V�X�i���j�A���C�g�L�l�V�X�i�����j�Ȃǂ̕��\�͂ɂ킩��Ă���B
�@�G���p�V�[�́A�e���p�V�[�Ɏ����\�͂����A�����̂��v�O�ł͂Ȃ�����Ȃ̂ŁA�A���ȂǂƂ��S�Ō𗬂��邱�Ƃ��ł���B�܂��A�������������Ɛ��_�I�ɃV���N�����āA�����������邱�Ƃő���̏���������Ƃ��ł���B
�@�{�f�B�G���n���X�́A���̂�̓��̂��ӎ��I�ɑ��삷��\�͂ŁA��Ӌ@�\���������Ď��_���[�W���Đ�������A�ؗ͂┽�����x�����I�ɍ��߂邱�Ƃ��ł���B�������A���ꂾ���ł͂Ȃ��A���̂�ό`�����āA���̐l�Ԃ⓮���ɕϐg���邱�Ƃ���ł���̂��B
�@�����āA�Ō�̃q�[�����O�́A���������a������\�͂��B����ꂽ�튯���Đ����邱�Ƃ͂������A���S���ĊԂ��Ȃ��������Ȃ�h�������邱�Ƃ��ł���B
�@���̓���T�C�I�j�N�X�\�͂́A��ʓI�ȂV�n���̃T�C�I�j�N�X�\�͂Ɋ܂܂�Ȃ��T�C�I�j�N�X���ׂĂ��Ӗ����Ă���B�t�Ɍ����ƁA�����ɂ́A����Ƃ������ȃT�C�I�j�N�X�\�͂����Ƃ��Ƃ��܂܂�Ă���̂ł���B
�@�����ӂ��̃T�C�I�j�N�X�\�͂ł��A�L���Ȑ��ݔ\�͂̎�����͐��S�l�ɂЂƂ肵�����݂��Ȃ����A����T�C�I�j�N�X�ɂ��Ȃ�ƁA���̔䗦�͐����l�ɂЂƂ�̃I�[�_�[�ɂ܂Œ��˂�����B���ꂾ���ɁA���̓���T�C�I�j�N�X�\�͂́A�^�ɋM�d�ł��������̂Ȃ��˔\���ƌ����邾�낤�B
�@�������A����ł���Ƃ������Ƃ͂������ɂ��ꂾ���ŋM�d�Ȃ̂����A�Ƃ�����ƁA���܂�ɓ��ꂷ���ĒP�ɂ߂��炵�������̔\�͂ŏI����Ă��܂����Ƃ�����B
�@���ɔ\�͂����p�ł���͈͂��L���A�e�n�����Ƃɂ�������̔��W�\�͂�����ʃT�C�I�j�N�X�Ƃ͈قȂ�A����T�C�I�j�N�X�͂����ЂƂ̌��肳�ꂽ���Ƃ����ł��Ȃ������������B���̂Ԃ��|�ɏG�łĂ���킯�����A���̌|�����ɗ����Ȃ����̂������肷��ƁA�܂��������b�ɂȂ�Ȃ��̂ł���B�����ŁA�Q�[���̒��ł̓���T�C�I�j�N�X�\�͂́A�{���̈Ӗ��ŏd�v�Ȃ������̔\�͂ɍi�肱��ł��܂����Ƃ��ł���B
�@�g�D���[�������ł́A�Љ�i���邢�́A�������̂��́j�ƃT�C�I�j�N�X�͂킩���������قǖ��ڂȊW�ɂ���B���ƌ����Ă��A�ߋ��̗��j���炵�āA���͂ȃT�C�I�j�N�X�̔\�͂Ɍ㉟������ĕ��������B���Ă����̂�����A��������R�̂��Ƃł͂���̂����B
�@�������A���݂ł����������Ȃ��A�����Ⴍ�Ȃ��Ă��܂����Ƃ͂����A�{���T�C�I�j�N�X�\�͂̎�����͌����Ă߂��炵�����݂ł͂Ȃ������B���݂ł��A�L���Ȃ����̐����ɒB���Ă��Ȃ������ŁA�킸������̃T�C�I�j�N�X�̐��ݔ\�͂������Ă���l�ԁi���Ƃ��A�������܂ɋ�������ǂ݂Ƃ�邾���̔���ȃe���p�V�[�\�͂̎�����Ȃǁj�܂Ŋ܂߂�ƁA���̐l���͖c��Ȃ��̂ɂȂ邾�낤�B
�@���̂��߁A��ʂ̕�炵�ɂ�����T�C�I�j�N�X�̐Z���Ԃ�ɂ͖ڂ���������̂�����B
�@�����ŁA�T�C�I�j�N�X�ƎЉ�̌��т����킩��₷�����邽�߂ɁA�ЂƂ̗�Ƃ��āA�Q�l�܂łɈ�ʃT�C�I�j�N�X�\�͂ƐE�Ƃ̊W�������Ă������B
�@�������A�����ɋ������T�C�I�j�N�X�\�͂ƐE�Ƃ̊W�͂����܂łЂƂ̗�ɂ����Ȃ��̂����A�������Љ�̒��ŃT�C�I�j�N�X�̐�߂Ă�������́A����ł������������������ƂƎv���B
�@�g�D���[�������͍L��Șf�����E�ł���B���̑傫���́A�\�ʐςɂ��Ēn���̖�50�{�͂��낤���Ƃ����A�z�����͂邩�ɏ���X�P�[�����ւ��Ă���B�������A���ꂾ���L��Ȑ��E�̂����A�l�ԑ����n�߂Ƃ���m�I�푰���Z��ł���̂́A�������ς��Ă��A�킸��10���ɉ߂��Ȃ��B�c���90���́A�l�Ԃ����ݓ��ꂽ���Ƃ̂Ȃ����m�̗̈�ł���A�L�j�ȑO�̖��J�̏�Ԃ̂܂܂ɕۂ���Ă���̂ł���B���Ȃ킿�A�g�D���[�������ł́A�����̏ے�����傢�Ȃ鎩�R���A�Ǝ�ȕ��������|���āA�f���̂قڑS����x�z���Ă���ƌ������Ƃ��ł���B�����āA�������̗Y��Ȏ��R�́A�����̕ω��ɂ����������Ă���B�g�D���[�������́A�܂��ɐ����̂�ڂƌ����ɂӂ��킵�����E�Ȃ̂ł���B
�@�g�D���[�����������̂悤�Ȑ����ɖ������ӂꂽ���E�ɂȂ����̂��A�����Ă䂦�Ȃ����Ƃł͂Ȃ��B
�@���̗��R�Ƃ��ẮA�܂����ɁA�������̎��R���A���炭�ς�炴�関�J�̏�ԂɂƂǂ܂��Ă��邱�Ƃ��������邾�낤�B�������̎��R���A�ω��ɂƂA���т����������̐�������ނ��Ƃ��ł����̂��A�����̊����Ȃ���Ԃ���������������Ȃ̂ł���B
�@�g�D���[�������ł́A�������Ēa�����������̐V���Ȃ鐶�����A���邳���l�ԂɎז�����邱�ƂȂ��A���������R�����̔g�ɂ��܂�Ȃ���A��̑����������āA�I���Ȃ��i���ƖŖS�̃T�C�N�����J��Ԃ��Ă����̂ł���B
�@�����āA���ɁA�������̎��R�̎��A���ɗނ����Ȃ��قǂ̖L�`������������B
�@�g�D���[�������́A�f���Ƃ��Č���ƁA�S�̓I�ɉ��g�ʼnJ�̑������E�ł���B���̂��߁A���������イ�ŁA���܂��܂ȐA�����Ԃ��炩���A�}��L���āA�ɉh�̌���������Ă���B���̂��肳�܂́A���Ȃ���A�ʂĂ��Ȃ��L����W�����O�����f���S�̂������ۂ�Ƃ݂���ł��邩�̂悤�ł���B�g�D���[�������́A�����ʂ�A��������f���Ȃ̂ł���B
�@���̂����A�������̕\�ʐς̂R���̂Q���߂�C�m������B���̊C�́A�ɂ�����ꂽ�嗤�����A����Ɍb�݂��L���ŁA�����̐����ɂ������ƓK���Ă���B
�@���̔엀�ȃW�����O���ƌb�ݑ����C�m���A����A����țz����ƂȂ��āA�������̑��푽�l�Ȑ������ݏo�����̂ł���B
�@�Ƃ�����A���̂悤�ɂ��ăg�D���[�������́A�z�����������̂���Ƃ����鐶�������G�R�ƂЂ��߂��������E�ƂȂ����̂ł���B
�@�������ɂ́A�������߂��ɐ������Ă�����A�T���Ƃɂ���Ă��̑��݂��m�F���ꂽ�肵�Ă悭�m���Ă�����̂����ł��A���т����������́A���܂��܂Ȏ�ނ̐��������������Ă���B
�@���̂����A�l�m�ꂸ�Ӌ��̉��[���ɐ������鐶����������B���̂悤�Ȑ����ɂ́A���Ɋ�Ȃ��̂���قȂ��̂������A���̎�ނ��܂��c��Ȑ��ɒB����Ǝv����̂����A���ۂɊm�F���ꂽ��́A���̂����̂��������ɂ����Ȃ��B�{���ɉ����������Ă��邩�Ƃ������ƂɂȂ�ƁA�z���ɗ��邵���Ȃ��A�������Ă������Ă��������Ȃ��Ƃ��������悤���Ȃ��̂ł���B
�@�������A�������̎��R�E�ɐ������鐶�����ɂ́A�������̌����ȓ�����������B
�@���Ƃ��A�g�D���[�������ɂ́A�����̏Z�ނ��̑��z�n�̘f���ɐ������Ă��鐶�����̂����A�唼�̂��̂��������Ă���B�����ɂ́A�L�A���A�r�A�T�Ȃǂ̚M���ނ�����A�g�J�Q�A���j�Ȃǂ���ށA�J�G���A�C�����Ȃǂ̗����ނ�����B���⍩����������B�܂��A�A���ɂ��Ă������Ȃ̂ł���B���ɖڂ��Ђ��̂��A�g�D���[�������S�y�ɐ�������V��̋����������B
�@���̐V��̋��������́A���Ă̓ݏd�œK�����Ɍ��������ԂƂ͈���āA�ϋv�͂ɂƂ݁A���������₭�A���o��m�\�̓_�ł����イ�Ԃ�Ȕ��B�𐋂��Ă���A�����āA���������Q�̓K����������Ă���B���������́A���C��ƁA�������̂���Ƃ�����̈�ɐ������Ă��邪�A������ނ�̎������ꂽ�K�����䂦�̂��Ƃł���B
�@����Ӗ��ł́A���肠�܂�قǖL���ȃ������̎��R���A�����̑�^��ނݗ��Ƃ��A�ނ炪�����c��A���x�Ȑi���𐋂���̂��㉟�������̂ł���B����A�������ɐ������Ă��鋰�������́A���̘f���̖L�`�Ȏ��R�̐\���q�ƌ����ׂ����݂Ȃ̂ł���B
�@�������A�g�D���[�������ɂ́A�����̏Z�ސ��E�Ɠ������A����Ƃ悭�����������̑��ɂ��A�܂��������ɂ͌����Ȃ��悤�Ȑ��������������݂���B
�@���̒��ł��A�������Ǝ��̐������Ƃ��čł��ے��I�Ȃ��̂ɁA�g�ϐ��b�h�Ɓg�����b�h������B
�@�ϐ��b�i�k���E�r�[�X�g�j�Ƃ����̂́A�O�������ӂ��̐������Ɠ��������A�\�͂���Ȃǂ̓_�ő傫�ȕω��𐋂��A�I���W�i���̐������Ƃ͂܂������Ⴄ�����ɂȂ��Ă��܂����ˑR�ψّ̂̂��Ƃł���B���������ƁA���\�ȓ��H�A���}�W���Ƃ��A���s�����уG�C�Ƃ��ł���B
�@������A�����b�i�L�}�C���j�Ƃ́A�����̐������̔\�͂�O�������킹���������̂��Ƃ��Ӗ�����B���Ƃ��A�N���ƃJ�j���|�����킹���悤�Ȑ������Ƃ��A�g���ɃR�E�����̗��₵���悤�Ȑ������Ȃǂ����݂���̂ł���B
�@�������A���R�E�̂��Ƃ��������A���̂悤�Ȑ������������Ȃ��Ƃ��납�琶�܂�o�Ă���Ƃ͐M�����������Ƃł���B����͂����܂őz�������A�����炭�����b�́A��j�����l�����o�����l�H�̐����̂��낤�Ǝv����B
�@���ۂ̂Ƃ���A���̍����b��ʂɂ��Ă��A��j�����l���g�D���[�������̎��R�ɂ��������e���͑���Ȃ��̂�����B�}�V���r�[�X�g�̒��ɂ́A�쐫�����Ė{���̓����̂悤�ɕ�炵�Ă�����̂����邪�A�\�ł́A�@�B�ƗL�@���̓��̂����킹���A�T�C�{�[�O�̂悤�Ȑ������܂Ő������Ă���Ƃ������Ă���̂ł���B